「音韻」について
公開 2023-02-22
変更 2026-02-17
詞「音韻」は、第1義である「発話/SPEECHされた音声/VOICEの、言語音としての/LINGUISTIC、心思(=思考)へのひびきかた/SOUND PROPERTY FOR APPRECIATION」として日中において一般に使われている*1 この詞「発話」に対しては中国語では説・講・言・叫などが適時に使われ、現在の詞意として、説・講/SPEAK&EXPLAIN、話/WORDS&TALK、語/LANGUAGE&ILLOCUTION、言/TONGUE(説・講・話・語の上位概念へと詞意が歴史的に変化した)、叫/CALL&YELLとの基本的なつかい分けがあるようだ またここでは音声/VOICE≙声道音/VOCAL TRACT SOUND(中国語で口音)とする 中国語での基本字義としては、声/SOUNDは低レベルでの単なる音響現象、音/SOUND (=SOUND PATTERN AS SIGN)は記号としての音響パターン、楽/MUSICはリズム・メロディーにもとづいた音楽を指し、日本語詞「音」の意味全体には中国語の「声音」がおよそ1対1対応する また日本語詞「声」は原義をはなれ音声のみを指す場合がほとんどである点が中国語と大きく異なり(@漢辞海)、結果的に日中交じり句において詞「声」は単独では使いにくい
音韻の「韻」は、韻文(ライム構造でリズムづけられた書面語文)・那智滝の韻(ひび)き(音に付帯する現象の様子全般)・竹韻(竹林が風にそよぐ現象の様子全般)・冬韻/WINTER RHYME(冬の感覚効果を発揮する景物全般とくに景色)・飛鳥仏の神韻(神々しく発揮される霊威)・唐朝的韵味/唐代の風味や趣(余韻などの思考効果を放つ鑑賞・思慕の対象)の様に、事物つまり物体・現象・思考対象・受容器官等の各々が備えている「ひびき」(心思への和諧/HARMONIZE作用としての共鳴/RESONANCEを模擬して指す)に関する特性要素/PROPERTYにより、情動・審美に直結する鑑賞者の心思での印象/{IMPRESSION、MENTAL IMAGE}として、各々和諧的共鳴的に情動的音色が鳴ること/EMOTIONAL TIMBRE*13、つまりその事物に起因する鑑賞者への情動効果・審美効果への固有特性が発揮されることにつかわれる詞である
また「音韻」は「発話音声の言語音としてのひびきかた」のほかに、中国では鉄観音茶の果実香味の独特な喉ごしをさす詞でもあり*16、他に例えば武夷岩茶なら「岩韻(岩骨花香味の喉ごし)」など、飲茶要素における滋味と咽喉と心思の3が和諧する味嗅覚認知的な喉のひびきかた「喉韻」における相異/VARIATIONを「~韻」と名づけた例である(この場合にはひびきを発する主の事物は茶ではなくその受容を担う感覚器官としての喉が鳴る現象となり喉韻であって茶韻でない点に注意する 上の例では響きを発生しているのは滝・竹まわり・冬景物・仏・唐代心思となり特に対象の範囲にルールがあるわけではなさそう)

言語学におけるPHONOLOGYの分野(定義の1は人類発話音の構造とパターン系統の考究*2 別の定義の1は1つの言語共同体で相互理解の目的で使われている音的記号の考究*3)では、文学・日本語学(国語学)・言語学・音声学等からなる学術領域における歴史的経緯もふまえ、「言語学上音韻」と言い換えできる詞義にて「発話音声の言語音としてのひびき」との第1義から引伸して造られた学術用語「音韻」と、PHONOLOGYの訳語としての「音韻論」(「PHONO-」は科学において音響波/ACOUSTIC WAVE≜機械振動進行波/MECHANICAL VIBRATION TRAVELING WAVEをさす)と、が使われている(*4-5)
ひろく音声の音響物理的ひびきと、また別にひろく発話音の生産/SPEECH-SOUNDS PRODUCTIONにかかわる諸現象と、内心に形成される心理的な発話意図*6と、に関連する音声言語現象の全体から抽出/DETECT・模擬/SIMULATEしうる各種の言語要素において、発話行為の音論に属する「PHONETICS学」的言語要素の1である物理現象的なPHONEという発話操作のまとまり(人類に共通とみなせる発音の類型に対しての広い合意にもとづくアルファベットによる経験的記法に沿った発話音の時間分節を取り上げて扱うことを基本とする*2)を考究してきた学史に対向して、言語構成体の音論に属する「PHONOLOGY学」的言語要素の1でありその分類論が社会共有されているとみなせる抽象原理としてのPHONEMEという思考操作のまとまり(哲学分野での草創期の「構造主義」分野を意識した現象系統における断片/FRAGMENTのとらえかたであり、必ずしも時間分節やその配列のみを扱うものではなく、ある環境条件下でのPHONEとの1対1の関係が発音類別・分節タイミングともに併記できるというものでもない別次元の系統である)をあたらしく立てこれを考究することが、19世紀晩期から言語学 – PHONOLOGY学の現代手法として導入され様々に展開してきた*3
これにより、物理現象としてのPHONEの分節構造を解析する旧来の分類論の考察のみでは解けなかった音声言語の学術課題(EG. 特定条件下での言語的相異・系統的音変化/SYSTEMATIC SOUND CHANGEといった分類越境・再構成、比較法/COMPARATIVE METHODやその他の未知推測/INFERENCEをふくむ現象解析、社会における言語生成の原理究明など)に対して、発話意図により内的に形成されたもの(たとえば音素として代理的に表現する記号列)とそれに対応して外発された発話音現象における発話操作のまとまりにおける分配・重畳などの構造を決める組織原理面や、音素・発話音にも制約されない言語構成原理面などからの拡張的・効果的な考究ができるようになり現在まで発展・分岐してきた
PHONEMEは、別々の発話音系統間においても発話行為の音論であるPHONE分類論の主観的類似関係を代理的に利用して適当に共有すれば、その同意の前提・範囲のもとで、言語構成体の音論であるPHONEME分類論をもちいた議論が十分有効的にすすめられるといった性格のものである 日本語に対するPHONEME/音素は断りがなければローマ字表記に沿って母音・子音を別にあつかうアルファベット水準音素要素の配列をもちいて議論をするとの同意が現在までに形成されている
またPHONOLOGY学においてあつかいうる「言語要素」は、時間分節・要素配列性・発話音系統の社会的共有が必須要件というわけではなく、またこれを内心的な神経言語的認知/NEUROLINGUISTIC COGNITIONの指標/INDICATORとみる生理的アプローチとすることもできる さらにはPHONEMEとはさらに別の音論によらないまとまりを立ててもよく(EG.生成言語断片を操作子として都度評価により言語を順次に構成するプロセス)、またさらには「まとまり/UNIT」を操作して言語を構成する類の言語要素である必要もない(EG.通達コンセプトをなんらか符号化して通用言語則を満たした発話意図と相互変換するような新規法の探求)などと拡張的にとらえる余地がある
課題として、黎明期のPHONOLOGYにおけるPHONEMEの訳出には当初から様々な議論があった(*7-8) 特に詞「(言語学上)音韻」は、一般的に受けとられている現在のPHONEMEの対訳つまり「音素」だけでなく、調子を音韻に含めない(記法としての声・韻・調の3従属要素から調子部分をはぶいたものを要素注出的に指す場合であり中国語でも「声韻」として独立にあつかわれるものを日本語でさらに「音韻」と改名し追加した例)と限定したり、逆に音韻と音素’を混在させるときの音素’は言語学的プロソディーなど超分節要素を含まない(音韻はそれを含むものを別途指す)という前記「声韻」の意味でつかう流儀を(なぜか)とる学派*15など、それぞれの説は意味がとおるのだが結局の詞義が学術的にまとまらず混乱が放置される経緯が長くつづいてきた
金田一『国語音韻論』(1935)*9は言語学の新しい枝分野としてのHOSTORICAL PHONOLOGYをひろく国内に紹介した書であるが、詞「音韻」の扱いは、序および1章において旧来の音韻学への接続として(1)ことばがそれとわかる様にひびく物理現象と(2)類別された個別の発話音の音色/TIMBLE(=音質/QUALITY)それ自身をさして用いており、第3章以降に(3)PHONEME(言語学的操作子の1)の対訳として、“音声経験に基づいて心的に構成されている音声観念、即、音韻[/PHONEME]を形式とする伝統的心的記号の体系が国々にあって国語を成している”(金田一1963)との定義を立てて発話音に対して人が反応する内的な認知標識としての「(言語学的)音韻」を追加し、「(1)-(3)のどれも音韻と言って通じる」状態を指向すれば(便利でわかりやすいから)よいとの「これも音韻あれも音韻」案を推進する立場を出している 物理現象も個別音色もそれらへの音観念もすべてが「音韻」であり、このように定めた音韻を考究する学問が音韻論でいいではないかとの当時の言である
また学史においては、PHONEME・PHONEのそれぞれの訳出を、現在通用の音素・音価以外にも文法学声価・声音学声価としたり*10、現在中国語ではそれぞれを音位・音子と訳出する例もある さらに北京大の教科書例*11では任意の局所方言点における言語学的な音系(中国語の「語音系統」より短縮、和訳の発話音系統に対応)の発話音作用の最小要素の訳語を伝統的なPHONEME/音位(同じく「語音単位」より)とし、音声学的な発話音の最小要素をPHONE/音素(同じく「語音因素」より、和訳とは逆転混乱している例)と訳して、PHONEMEはPHONEに時間分節的に1対1対応する最小要素としての操作子であると書中では限定しており、これは言語学的分析において制約的であり初歩的な誤謬でもある 現在中国語訳にあらわれるPHONOLOGY/音系学は、PHONEMEの解析が研究の花形だった構造主義胎動期には現在日本訳と命名法が似た「音位学」と呼称されていた(PHONEME/音位をあつかう学だからPHONOLOGY/音位学でいいとの部分は金田一論理と同じ)が学術的経緯から改名が必要となり実施したという事情もある
いまなお、PHONOLOGY/音韻論、PHONEME/音素、PHONE/音価、とあてている日本語対訳の妥当性、および詞「音韻」の詞義・扱いについては、初学者・非当事者にとっても、抽象指標と物理現象との詳細関係がつかめない、(学派として)PHONEMEをPHONEの別水準分類と扱うのみ(EG.別解像度であらわす物理現象としての粗分類/BROAD DESCRIPTIONを単にさしPHONEの定義と本質的に同じと扱う用例が非常に多い PHONEの局所的・機会的な分類相異や複数PHONE分類の物理現象上グルーピングをさすことだけにもちいている例がこれである これらは音声連続に対しての科学技術的・機械的な言語分析・会話成立確認・発話認識が長い間不十分な学術水準であった学術史を背景*14にして、単にPHONEMEをPHONEのグループ分けが言語グループ毎に異なることの音響的な例示としか正確には論拠できなかった過去経緯を引きずっている)であって、PHONEMEとPHONOLOGYがそれぞれ学術上の別領域における音声言語要素である点をうまく扱っておらず結局は音声学の話題に終始する用例があまりに多い、また学術語の国内移行史(詞義のすり合わせや改変)の事情が整理されておらずよくわからない、など肝心な部分が不明瞭で、かつ時代的・属人的にも大きく揺らぎがあり、議論上の誤解・発散を誘引しやすいとの課題がなお根深く存在している*8
また「音韻」に相当する外国語としての詞・フレーズは、PHONEMEを除けば、英語圏では言語学の副分野としての「PHONOLOGY」と、音声言語現象から抽出できる各種言語要素をまとめた上位概念を指す「PHONOLOGICAL~」と、においてもっぱら現れ*12、PHONEME/音素と対訳を決めてしまえば、学術的個別概念の詞・フレーズとしての「(言語学上)音韻」の対応用語を不要として例えば単に(発話の)「音/SOUND」と表してすむ場合が大半であることもこの課題の解決に皆が無作為である原因になっている
これら課題を多少とも是正することを期待して、以下の既出学説の組を規範として選びだし、その一部には工夫を加えて、記事・話題におけるガイドラインを制作した:
●PHONEMEの訳は常に「音素」としてここに対する「音韻」訳は今後の議論につかわない また「音素」とはその最小要素としての操作単位/OPERATIONAL MINIMAL UNITのことを専ら指すものではなく、注目する音のまとまりを記号(列)で表したものを一般に指すとする この素に素子の意味はない 音系統/SOUND SYSTEMは旧来の音韻系統/PHONOLOGICAL SYSTEM(OF COMMUNITY)としたままでも、音韻がPHONOLOGICAL MATTER全体を指すため問題はない これらにより、過去にPHONEMEもその上位のPHONOLOGICAL MATTERもどちらも音韻と訳してきた誤謬を1つ解決できる 音韻系統つまり発話音パターン系統には物理現象を支配する音価の側面とコミュニティーに共有される音観念からなる音素の側面があり、音系統とは音価の系統も音素の系統もそれぞれ別視点で内在された概念であるとの立場をとる(Akmajian『言語学』4章結論を参照*2)
●音声学・言語学的な意味でのPHONEの訳は「音価」とする
●詞「音韻」の使用を以下の条件のいずれかに制限することで、議論上の混乱・遅滞を積極回避する:
― 発話された音声の、言語音としての物理的ひびきとの第1義でつかう「音韻」
― 音声・発話音・音価・音素・非分節言語要素・言語リズム要素・言語化コンセプト始源要素・実言語変換構成機序要素・発声運動要素など、音声言語に関連する諸現象から抽出できる各種の物理的・心理的言語要素をまとめた上位概念である「音韻」(~PHONOLOGICAL MATTER)、またそれを対象にする言語学の枝分野としての「音韻論/PHONOLOGY」
― 古代書面語において、各時代における読音やその相異・分配状況・通時変化(脱落・縮約・転換・簡易化・明瞭化など、発話音系統での音価・音素マッピングの変化やその他の孤立変化)を推測するなど、各時代に各地域・各集団で共有された誦読音や口述音の発話音系統を、音価・音素などの言語要素をつかって、韻文や発話音海外翻訳文、また現代手法などから科学的に研究する「(歴史)音韻学」(=HISTORICAL PHONOLOGY)
― 詞「音韻」をつかうとき、これを「(LINGUISTIC)SOUND」と言い換えて自然なら、誤解を避けるためつとめて「発話音/SOUND」とする これを「PHONOLOGICAL MATTER」と言い換えて自然なら、直上3項いずれかに定義した意味としての「音韻」をつかう どちらでもなければ「音韻」それ自身について述べていないと一次判断して別の適語を再度さがしてみる
参照
1李思敬(慶谷寿信・佐藤進訳注)『音韻のはなし』(光生館1987、訳注に定評、初版正誤表、大学図書館でみつかる、原著はコンパクト書の『音韵』「汉语知识丛书」シリーズ、商务印书馆1985(重印版2001、ISBN978-7100030489))
2Akmajian, A.(アリゾナ大)他『Linguistics』(5 ed., MIT Press. 2001)
3トゥルベツコイ『音韻論の原理』(岩波1980、原著1958)
4風間他『言語学第2版』(東大出版会2004)
5商務印書館&英オックスフォード大『OXFORD ADVANCED LEARNER’S ENGLISH-CHINESE DICTIONARY』(7ED-3RD、2009)
6キャットフォード『実践音声学入門』(2版、大修館2001、対応原著はCATFORD『A PRACTICAL INTRODUCTION TO PHONETICS』(OXFORD U.P.1988))
7高山倫明EP(九大)『日本語学大辞典 – 「音韻史」条 – 概念項』(東京堂2018、P91)
8阿久津『音韻と日本語学習』(拓殖大逐刊2018、リンク先機関リポジトリーにPDF1MBあり:https://cir.nii.ac.jp/crid/1050564289020369792)
9金田一京助『増補 国語音韻論』(1935・1963)
10松下大三郎『標準日本文法』(紀元社1924)
11『语源学纲要 修订版』(4版、北京大学出版社2010)
12Pinker『Harvard’s Steven Pinker: how we speak reveals what we think』(文字起こしつき本人出演ビデオ50分、BIGTHINK誌2012、参照2024-10-26:https://bigthink.com/videos/how-we-speak-reveals-how-we-think-with-steven-pinker/)
13LIU『Emotional Connotations of Musical Instrument Timbre in Comparison With Emotional Speech Prosody Evidence From Acoustics and Event-Related Potentials』(Frontiers in Psy.2018、リンク先にPDF2MBあり:https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2018.00737/full)
14服部『新版 音韻論と正書法』(大修館1990)
15衣畑編『基礎日本語学』(2ED、ひつじ書房2021)
16阮『中国茶芸』(山東科学技術出版社)
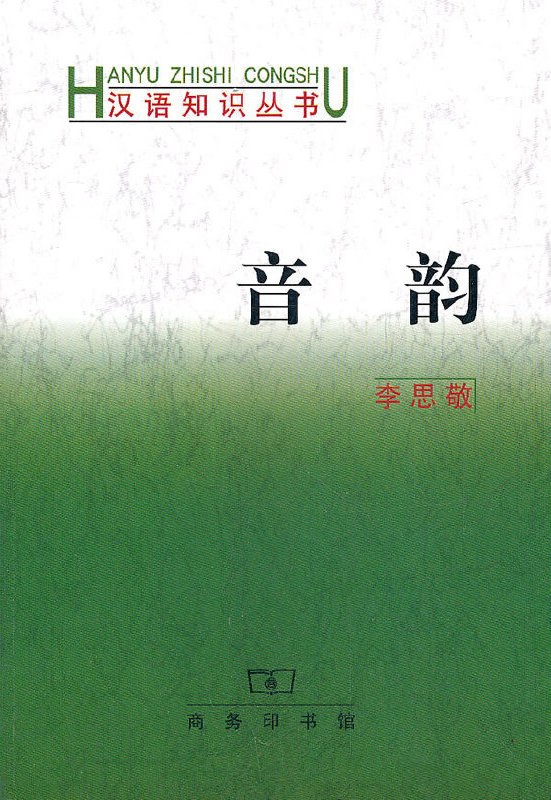
///
ピンバック: IPA音声記号により声道音を符号化することを工学的に表現してみる – ティー・フォー・ハーツ
ピンバック: IPA音声記号により声道音を符号化することを工学的に表現してみる ― ENGINEERING EXPRESSION OF IPA PHONETIC ALPHABET FOR ENCODING VOCAL TRACT SOUND – TEA FOR R2
ピンバック: 語:詩・歌・曲・謡・咏・唱・誦・念・賦・文・詞・辞・諺・節・楽・韻・律・調の中国新華字典におけるつかいわけ – ティー・フォー・ハーツ