紫霞のみち(古文漢文の学びなおし) ― ASCENDING WITH PURPLE HAZE
公開 2023-10-01
変更 2025-11-16
『源氏物語を古籍の影印本で読んでみる』『白氏文集巻子本(鎌倉時代)の「華原磬」』『長恨歌と長恨歌伝』『紫式部公園の紫式部人形』のつづき
—
源氏物語鑑賞へのアプローチとして、古文・漢文にあらかじめ習熟しておくための課題図書を選択しその学びかたをまとめた 高校国語課程はすべて忘れている前提ではじめる
1、古文の課題図書
以下の順序で古文の読解になれていく(ウエブでひろった予備校講師による受験古文の読解学習ノウハウを転載したもの 易 – 難で学校古文の推奨学習順にならぶ)
1-1、宇治拾遺物語
1-2、十訓抄
1-3、徒然草
1-4、平家物語
2-1、伊勢物語
2-2、大和物語
2-3、大鏡
2-4、更級日記
3-1、枕草子
3-2、源氏物語
2、漢文の課題図書
紫式部が源氏物語で参照したであろう漢文古書*1の有名どころは、訓釈書などを使って注解つき中国語正文にふれておく:
●白居易の自著全集(書名は『白氏長慶集』『白香山詩集』など)
●史記(三家注のもの)
●漢書(顔師古注のもの)
●文選(李善注のもの)
3、課題図書のよみかた
●上記の課題図書は、古文であれば連綿かなで、漢文であれば中国語でなんとかよみたい 平安時代は、古文なら連綿かなでの写本、漢文なら楷書での写本を巻子本でくるくる読んだのだろうけど、前者は入手できる古代(ここでは日本の古代≜応仁の乱より前としている、以後は祖現代・現代の扱い)の墨書写本など古籍の影印書で、後者は古代(ここでは中国の古代≜五四運動C.1919より前としている、以後は現代の扱い)の木版印刷書など版本の影印書でためしてみる
●古語正文・注解・現代語訳を参照するなら以下の訓釈書が初学者向けで市価が安めだった:
― 大島建彦注『宇治拾遺物語』(新潮日本古典集成シリーズ、新潮1985、全訳はないが集成の部分訳注で十分読める)
― 泉基博『十訓抄 ― 本文と索引』(笠間書店1981、書陵部カタカナ本に対する全翻刻と総詞索引 全訳はないが十訓抄は児童書でもありなんとか読める)
― 木藤才蔵注『徒然草』(新潮日本古典集成シリーズ、新潮1977、部分訳注のみで全訳はないが他書にもいろいろ良訳が見つかるだろう)
― 杉本啓三郎『新版 平家物語 全訳注 1-4』(講談社学術文庫~2017、一方流系列の流布本である覚一本を充実した注解でじっくり鑑賞できる また水原一の吹き込んだNHKのカセットテープ65集があり八坂流系列の120句本の朗読だがその口述訓釈とあわせ引き込まれる楽しい内容である)
― 片桐洋一『伊勢物語全読解』(和泉書院2013、やすくないが親切)
― 高橋正治訳注『竹取物語 伊勢物語 大和物語 平中物語 – 大和物語』(5版、日本古典文学全集シリーズ、小学館1976)
― 保坂弘司『大鏡 全現代語訳』(講談社学術文庫1981、全訳注だが古文の正文がなく正文は大系などで参照する)
― 犬養廉訳注『和泉式部日記 紫式部日記 更級日記 讃岐典侍日記 – 更級日記』(日本古典文学全集シリーズ、小学館1971、江國香織全訳2016(河出文庫2023でも)もある)
― 渡辺実注『枕草子』(新日本古典文学大系シリーズ、岩波1991、「3巻本」版正文への注解 「能因本」版正文にもつかえる 全訳がないので全集などを参照する)
― 玉上琢弥『源氏物語評釈 全14巻』(角川書店~1964、やすくないが親切)
― 佐久節訳注『白楽天詩集1-4』(続国訳漢文大成シリーズ、国民文庫刊行会1928、ふるいが全訳はよみやすく日本図書センターからの復刻『白楽天全詩集1-4』もあり入手困難でもない)
― 小竹文夫他訳『史記I・II』(筑摩世界文学大系6-7、筑摩1971、本文全訳が主で注はわずか ちくま学芸文庫1-8と内容同じ)
― 小竹武夫訳『漢書1-8』(ちくま学芸文庫~1997、本文全訳と小竹注)
― 『文選』(新釈漢文大系シリーズ、明治書院、やすくないが本文全訳・訓釈はこれと全釈漢文大系シリーズ7冊(集英社~1974)から大部分が参照できる)
参照
●段『『源氏物語』における『白氏文集』引用の特色』(北陸大学紀要2008)
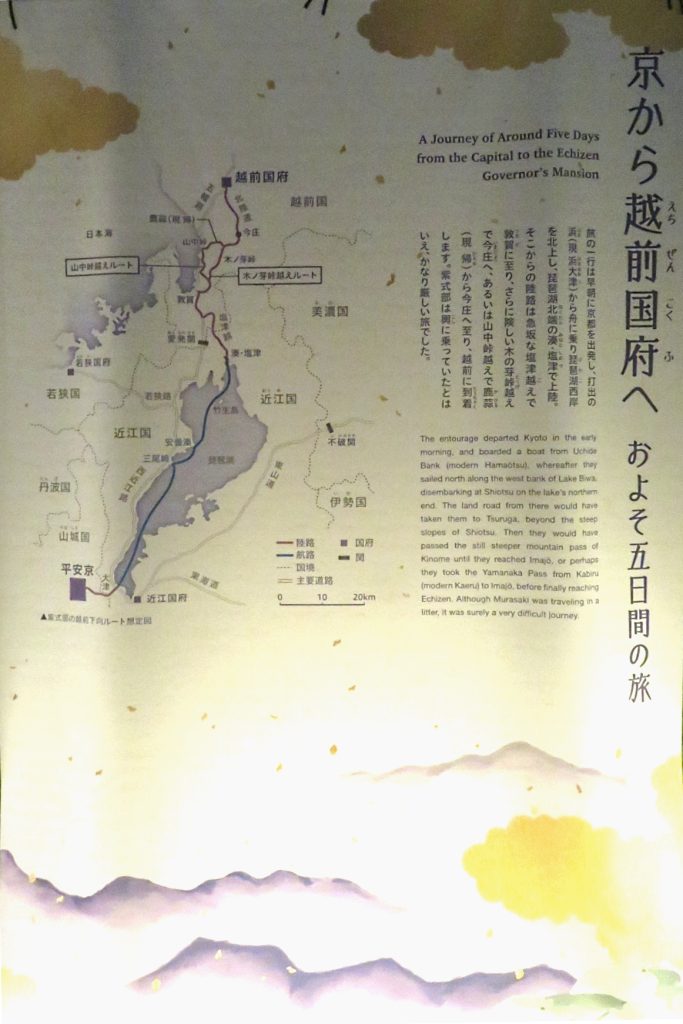



///